第5章:仕上げで差がつく!AIライティング後の編集・推敲の極意
AIが生成した記事は“たたき台”に過ぎません。
本当に読者の心に届く記事にするには、**人の手で磨き上げる「編集と推敲」**の工程が不可欠です。
この章では、私が実践している“仕上げ”のステップを具体的に紹介します。
1. AI原稿は「下書き」だと割り切る
AIは優れた文章生成ツールですが、読者に刺さる文章には“温度”や“人間味”が欠けることも。
まずは、AIの出力をそのまま使うのではなく、「ここからどう仕上げよう?」という視点で見直しましょう。
この段階では、「自分の言葉に言い換える」「不要な言い回しを削る」「体験談を加える」といった、自分らしい味付けが重要になります。
2. 読者視点で見直す「推敲チェックリスト」
推敲とは、ただ誤字脱字を直すだけではありません。
**読者にとってどう伝わるか?**という目線で文章を再評価することです。
以下のチェックリストで確認しましょう:
- 最初の3秒で読者の興味をつかめているか?
- 結論がぶれていないか?
- 同じことを繰り返していないか?
- 難しい言葉や専門用語は丁寧に言い換えたか?
- 次に進みたくなる文末になっているか?
- 読者の「悩み→解決」の流れが自然か?
この推敲だけでも、読者の離脱率は大きく下がります。
3. 言葉を“磨く”ポイント
言葉選びは記事の印象を左右します。
以下のような工夫で、伝わる記事に仕上げましょう。
- 抽象語は具体化する(例:「すごく良い」→「朝の30分で集中力が続いた」)
- 視覚的にイメージできる表現に変える(例:「すばやく」→「3クリックで完了」)
- 繰り返し表現は避け、類義語でリズムをつける
- 肯定的な言い回しで読者の感情を引き上げる
さらに、「自分の言葉で語れているか?」を見直すと、ぐっと親しみのある文章になります。
4. 見た目も整える:段落・改行・強調の工夫
文章が読みやすいかどうかは、視覚的な設計にも左右されます。
- 1文1メッセージの意識で改行する
- 長い段落は分割して読みやすくする
- 太字や 斜体 を活用して、要点を強調
- 箇条書きで情報を整理
特にスマホ閲覧が多い現在、行間や改行の使い方が読了率に直結します。
5. CTA(行動喚起)を忘れずに
記事を読み終えた読者に「次の一歩」を提示しましょう。
- 関連記事へのリンクを置く(「こちらの記事もおすすめ」)
- SNSでのシェアを促す(「この記事が役立ったらシェアしてね」)
- コメントを求める(「あなたの意見も聞かせてください!」)
- メルマガ登録やLINE登録に誘導する(「限定特典はこちら」)
読了後に“何もしない”を防ぐための工夫を意識しましょう。
まとめ:記事は「書いて終わり」ではなく「仕上げで始まる」
AIが生み出した原稿に、あなた自身の言葉・視点・感情を加えることこそが、 本当に読まれる記事への近道です。
編集・推敲まで丁寧に取り組めば、 あなたの記事は確実に“他とは違う存在”になります。
次章では、いよいよ「収益化の仕組み化」について突入していきます!
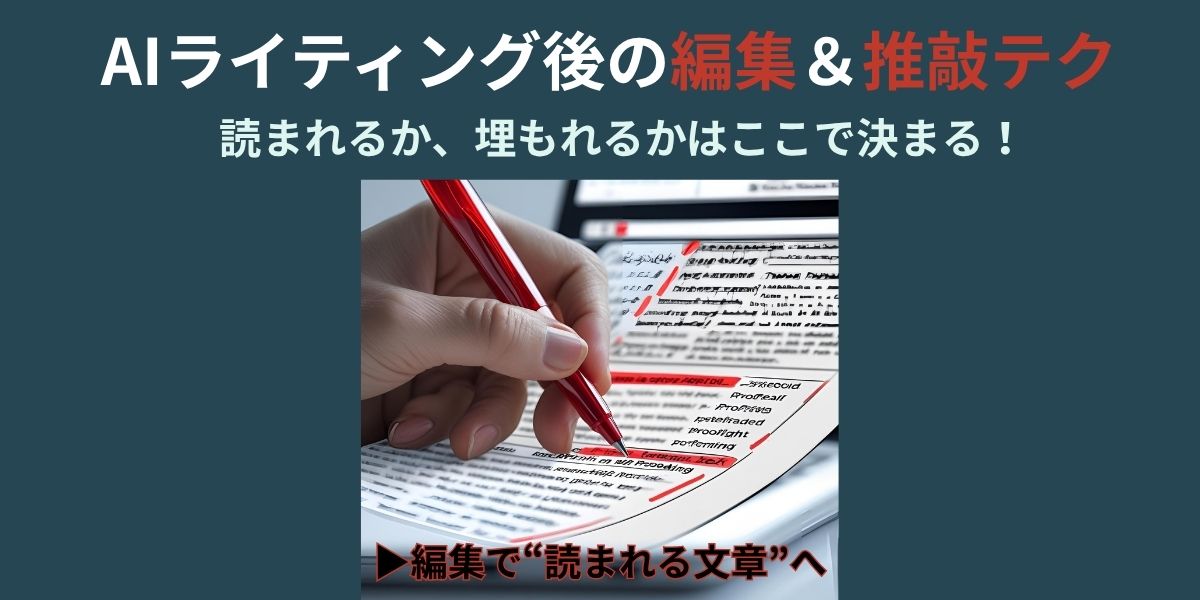
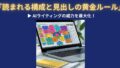

コメント